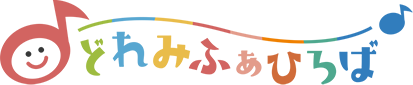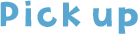台詞がないからこそ心に届く──『Flow』ギンツ・ジルバロディス監督に聞く”想像力を育む”アニメの秘密
2025.03.01

2025年米アカデミー賞長編アニメ賞、国際長編映画賞(ラトビア代表)ノミネートとなる世界の映画賞で賞賛されている無声アニメーションが日本で3/14(金)から公開になります。
それは洪水に見舞われた世界で、動物達と旅をする猫の視点から世界を見つめる映画『Flow』です。台詞が無いので子どもにも理解でき、動物しか登場しないので飽きることなく物語に没入出来る。そんな魅力が詰まった本作で来日したギンツ・ジルバロディス監督に、アニメ映画の作り方や無声アニメだから育める想像力についてお話を伺います。
映画『Flow』ギンツ・ジルバロディス監督インタビュー

ーー 前作『Away』(公開:2020年)も台詞はありませんでした。今作では動物達の鳴き声での表現。監督が台詞に頼らない理由はなんでしょうか。
監督:これまで私が作った映画はすべて台詞がないので、今回の映画でも台詞を使わないようにしたいと思っていました。台詞がないからこそ、他のツールや音楽を使って、より表現力が豊かになります。そのお陰でより映画的になると思っているんです。
そもそも私が好む映画や好きなシーンには台詞がありません。とても視覚的で、映像と音楽がどのように連動するかを重視しているからです。自分的にはカメラの動きや照明など視覚的に訴えるものを通して表現するほうが、観客に伝わると思っています。
ーー 猫だからなおさら瞳孔の開き方や身体の伸び縮みなどで、感情が見えてくるのだとこの映画から教えて貰いました。
監督:猫は身体全体で感情を豊かに表現します。実はこの映画では鳴き声も本物の猫の声を使っています。この映画は音響デザイナーが鳴き声を集め、猫の演技を創り出しています。それにカメラが猫の姿を追い、時に猫の目の役割を果たすので、観客が猫の気持ちを理解していきます。それだけで猫が何を考え、どう感じているかを表現出来ると私は思っています。そして、劇中に登場する重要な存在である水は、映画の中では比喩のようなものでもあります。
「カピバラの鳴き声は子ラクダの鳴き声を使うことにしました」

ーー 猫の声は本物なんですね。その他の動物、犬やキツネザル、カピバラの鳴き声はどうなんですか。
監督:犬も本物です。犬の鳴き声もそれぞれ特定の種類を使用しています。
唯一本物を使用していないキャラクターはカピバラです。音響デザイナーが動物園に行ってカピバラの鳴き声を録音したのですが、仔犬の鳴き声のようにキャンキャンしていたので、使える音ではなかったんです。というのも物語上、カピバラは性格的に平和的でのんびりしたキャラクターにしていたのでイメージと違い過ぎました。それでカピバラの鳴き声は子ラクダの鳴き声を使うことにしました。
ーー フランス映画の『リンダはチキンがたべたい!』(公開:2024年)や日本映画『化け猫あんずちゃん』(公開:2024年)などは、声を先に録ってからイラスト(3D)を作り上げています。今作はどうだったのですが。
監督:最初にキャラクターイメージを作りました。サウンドはポストプロダクション(技術的仕上げ作業)の最後の数週間で完成するのが通常ですが、今回、音響デザイナーは7ヶ月間作業しました。彼はアニメーション完成前から作業を開始し、最終的にサウンドと映像の組み合わせでどのように見えるかを想像しなければなりませんでした。なぜなら、この作品には台詞がない分、サウンドが非常に重要な役割を果たすため、十分な時間が必要だったからです。
私は音楽が無いことで音を感じることができる長いシーンをいくつか望んでいました。特にアニメーションでは非常に稀です。通常、音楽は常に映像と共にあり、何かを感じさせ伝えています。けれどその手法は多くを伝えすぎていると私個人は思っています。音だけで、自然や水や風を聞くことができるシーンがいくつか欲しかったのです。実際、音響デザイナーはそのことに少し不安を感じていました。でも下手に音楽を入れてしまうと観客にダイレクトに「観ろ」という指示するような感じになってしまうので、それは絶対に避けたかったんです。あくまでも自然に、そのまま動物達の視線を感じてもらうことが大事なので、音楽は無い方がいいと思いました。
時代を超越したオリジナル空間づくりの秘密

ーー 全体の世界観が、まるで海外旅行をしているような気分になりました。ロケハンなどをして、実際に見たものを映像に反映しているのですか。
監督:これは現実世界を舞台にしていない一種のファンタジー作品です。だから私たちは様々な場所を見て、それらを組み合わせてオリジナルで空間を作り出しました。それと現代のテクノロジーといえるガラスや金属の高層ビルなどは、劇中、使いたくありませんでした。
私の意図は時代を超越した感じ、いつの時代でも設定可能なものにすることでした。もし現実の場所を舞台にしてしまうとコントロールすることが出来ないからです。あくまでも自分たちは本物の世界ではなく、自分たちが考える物語の世界の映像を考えていきました。
ーー 少しベネチアの印象も受けました。
監督:確かにヨーロッパからの影響も多少あります。マヤ建築、チベットのようなものもあります。観客が主人公の猫と同じように初めて見る光景を感じてもらうということでした。どこかで見たことがある風景だと我々は思うかもしれませんが、猫にとっては全てが大冒険なので、「凄い、凄い」と一緒に初めての感覚を味わって欲しいと思い作りました。
「カメラを物語を伝えるツールとして使っています」

ーー マヤやチベットという言葉に納得です。
カメラワークが非常にダイナミックで、確かに動物達と大冒険をしている感覚を味わいました。沢山の映画を観られていると思いますが、影響を受けた作品はありますか。
監督:ええ、アニメ映画ではありますが、カメラワークに関しては、実写映画の監督の影響が大きいです。カメラを物語を伝えるツールとして使っています。単に機能的であるだけではありません。ただクローズアップ、ワイドショットだけを使うのは好きではありません。私はカメラもひとつのキャラクターとして物語を伝える手段として大事にしたいと思っています。猫の冒険にカメラも一緒について行くような感じです。だから風が吹くとカメラも揺れます。あと猫が主体であり、猫の目で全てを見ています。言うなれば猫の目がカメラなんです。キャラクターのすぐ近くにいて、遠くから観察しているのではなく、動物達のすぐ隣にいるんです。
ストーリーボード(絵コンテのようなもの)は使用しませんでした。視点が常に変化し、カメラが空中に上がったり水中に入ったりするため、すべての動きを描くのは不可能だからです。代わりに、3Dで直接アニマティック(各カットの画面構成をCGで映像化したもの)を作成しました。制作前にそのシーンの簡易バージョンを作成し、仮想カメラを使用して、ライブアクションのセットのように探索できます。これは、セットに到着してアイデアを発見するロケハンのようなものです。必要に応じて山を動かすこともできます。また、長回しのシーンは、これで行える唯一の方法でした。
すべては猫から始まった「重要なのは、敵対者や悪いキャラクターがいないこと」

ーー 影響を受けた実写映画はありますか。
監督:最も大きな影響を受けたのはアルフォンソ・キュアロンです。彼もロングショット(長回し)で知られています。(キュアロン監督作品は2013年公開の『ゼロ・グラビティ』、2019年『ROMA/ローマ』で米アカデミー賞受賞)
ーー 確かにアルフォンソ・キュアロンはその様にカメラを使用していましたね。
この映画は台詞がなく、動物の鳴き声だけなので子ども達にも届きやすいと思いました。
それぞれの動物たちの性格の違いが見えてきます。動物たちの性格はどのように構築していったのですか。
監督:そうですね…。
すべては猫から始まりました。10代の頃、私も似たような猫を飼っていて、その猫についての短編映画『Aqua』を作ったんです。シンプルな手描きの映画ですが、猫だけをテーマにしていました。その後、長編映画を作った時、もっとキャラクターを追加したいと思って、犬を飼ったんです。この映画に登場する犬は、自分の犬からインスピレーションを得たものです。
映画の中の猫は学習をしていきます。猫は最初はとても自立していて、その後、協力し合い、他の動物を信頼することを学びます。けれど犬は逆の方向に進むことを示したかったんです。犬は最初は他の動物達をとても信頼していて、いつも誰かに指示を求めています。でも、その後、より自立的になり、両者のバランスが取れてきます。独立していることと他人を信頼することの両方に良い面と悪い面があることを示したかったのです。
他の動物たちであるキツネザルやカピバラや鳥は、それぞれがチームを代表するようなものにしたかったのです。彼らが探しているのは、彼らが属する場所、受け入れてくれる誰かです。キツネザルは光輝く物を集めています。最初は知りませんでしたが、後にキツネザルは人や他の動物が光輝く物が好きなことに気づきます。それは一種の物質主義的な考え方でもあります。それは鳥も同様です。他の人に受け入れられることを求めています。
そこに平和的でのんびりした存在であるカピバラがいる。周りが喧嘩をしていてもカピバラが居るだけで皆をまとめてくれる、そんな存在を作りたかったんです。
重要なのは、敵対者や悪いキャラクターがいないことです。これらのキャラクターそれぞれに、観客である子ども達も共感できることを願っています。
大きなスクリーンで人生の手がかりを見つけて欲しい

ーー 人間社会を描いているよう思いました。
しかも鳥社会にいたっては、仲間ではない猫を庇った一羽の鳥を集団で置いていくエピソードもありました。
監督:彼らは本能に動かされて振舞う、とてもシンプルで典型的なキャラクターです。動物は本能に動かされていますが、人間も同じですよね。ですから、私たちはこれらの動物とそれほど違いはないと思います。実際、そういう時こそ人間の方が動物に似ている気がします。
ーー 子ども達はこの映画を観て、色々と考えると思います。
人間が作ったテクノロジーによって居場所を失っていく動物たち。映画では、そのテクノロジーが水で表現されていました。監督は映画にどのようなメッセージを込められたのですか。
監督:そうですね、私は映画を作りながら育ちました。私にとって最も重要なのはキャラクターである猫が、私たちの雰囲気をどう学んでいくかということでした。結局、猫が勇敢になることを学んでもすべてが解決するほど単純ではありません。現実の生活は、もっと複雑だと思います。猫は学んだとはいえ、最終的には不安を抱えたままです。少なくとも他のキャラクターが猫をサポートしています。
私は世界や人間に何が起こったのかには、あまり興味がありません。だからこそ、劇中、彼ら動物に焦点を当てました。ですが、手がかりをいくつか残しているので、観客にはその前に何が起こったのか、その後に何が起こったのかを考えさせることは出来たと思います。だから観客は自分の想像力でそれらを理解しなければなりません。特に最近のアニメ映画では、何が起こったのかなどすべてを直接伝え過ぎているように感じています。観客に実際に考えさせることによって、彼らはより積極的な物語の参加者になり、注意を払うようになります。この洪水は初めてではないかもしれませんし、最後でもないかもしれません。劇中にある様々な像がどこから来たのかを解明することは出来ませんが、観客には考えてもらいたいんです。
大きなスクリーンで色々なところに目をやり、「結局、どうなったんだろう?」と自分なりの解釈を持ってもらいたい。「こうやって生きていってもいいんだ」など、人生の手がかりを見つけて欲しい、感じて欲しいと思っています。
ーー 最後に子ども達にお勧めしたいアニメを教えて下さい。
監督:私としては宮崎駿監督の『未来少年コナン』をお勧めしたいです。
あのアニメの舞台は、洪水に見舞われた終末ですし。だからこの映画も影響を受けていますよ。

『Flow』3月14日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷他にてロードショー
監督:ギンツ・ジルバロディス
2024/ラトビア、フランス、ベルギー/カラー/85分 配給:ファインフィルムズ
映倫:G 文部科学省選定(青年/成人/家庭向き)
原題:Flow 後援:駐日ラトビア共和国大使館
(c)Dream Well Studio, Sacrebleu Productions & Take Five.
HP:flow-movie.com

伊藤さとり
映画パーソナリティ/心理カウンセラー。映画コメンテーターとしてTVやラジオ、WEB番組で映画紹介。映画舞台挨拶や記者会見のMCもハリウッドメジャーから日本映画まで幅広く担当する。
●連載一覧はこちら>>
関連記事
-
2024.10.24
-
2024.03.19